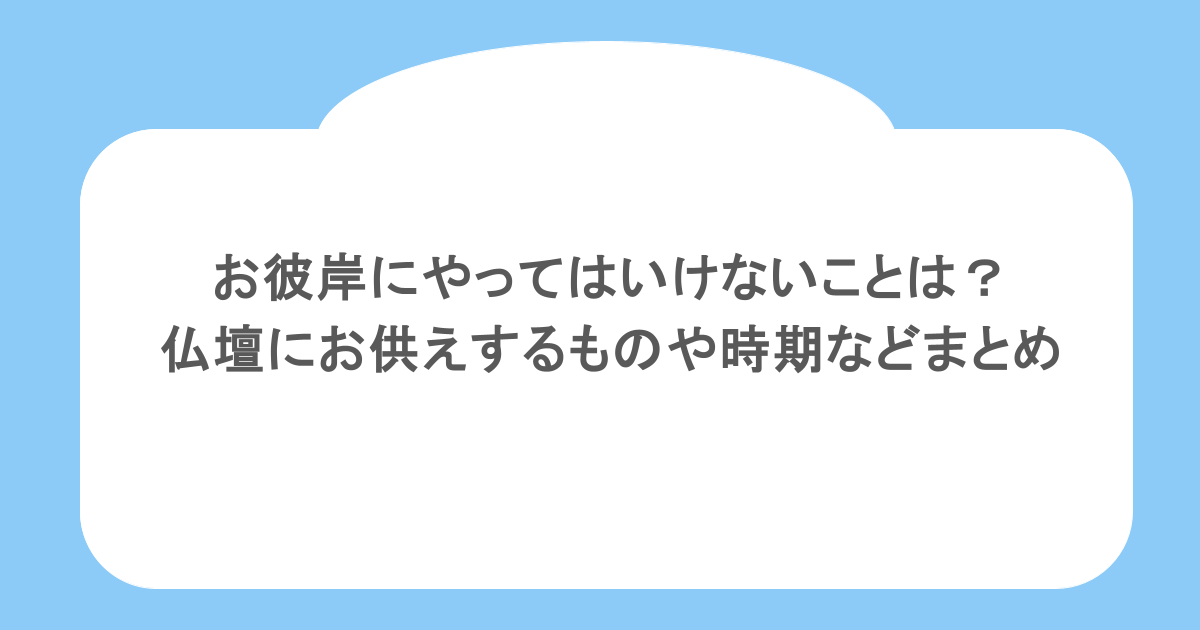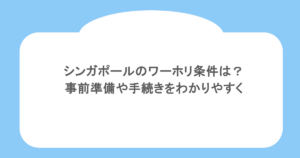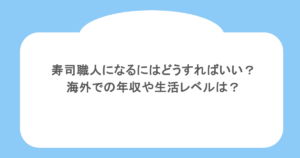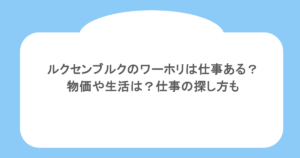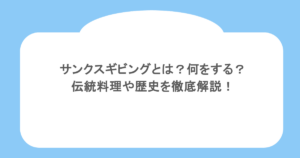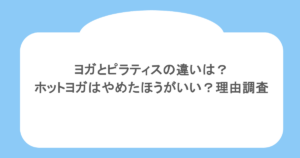お彼岸にやってはいけないことがあるのをご存知ですか?お彼岸は、亡くなったご先祖さまをご供養する仏教由来の行事です。お彼岸は、大切なご先祖さまのことを思い合掌する日でもあるため、やってはいけないことももあるようです。
日ごろ、健康で平和に生きられていることをご先祖さまに感謝するためにも、正しいお彼岸の過ごし方を知っておきましょう。
お彼岸の基礎知識からおさらい
まずは、お彼岸とはどういうものなのかをおさらいしておきましょう。お彼岸という言葉には2つの意味があります。「あの世」と「仏道の修行をおこなう期間」のことです。あの世へは、仏道の修行をおこなって初めて辿り着くことができるといわれているため、この2つが合わさって「お彼岸」の意味を成します。
もともとはインド・サンスクリット語が中国語に訳され「到彼岸(とうひがん)」となったのが、日本語で「お彼岸」と呼ばれるようになりました。しかし、お彼岸は日本独自の文化なのだそうですよ。
お彼岸の時期
お彼岸の時期は、春と秋の年2回です。お彼岸の目安は、カレンダーに書かれている「春分の日」と「秋分の日」を中心とした1週間を指しますので、厳密に期間がわからなくてもカレンダーを見て推測できますね。以下のように期間が決まります。
- 春:春分の日の3日前から数えた7日間
- 秋:秋分の日の3日前から数えた7日間
7日間ある理由
この記事でご紹介する「お彼岸にやってはいけないこと」を知る上で、そもそもお彼岸が7日間もあるというのは「長すぎる」「そんなに長い期間、やってはいけないことがあるなんて」と思う方もいるかもしれません。実は、お彼岸が7日間もあるのは、春分の日・秋分の日を除く6日間で「あの世へ行くための修行」をしなければいけないからです。
亡くなった人だけでなく仏道の修行をしていない私たちも、迷いや苦しみを無くすために、あの世に向けて祈りを捧げる日がもうけられていたのですね。
参考:Hankyu FOOD
仏壇にお供えするもの
仏壇にお供えするものは、ぼたもちやおはぎです。そのほかにも、季節の果物や日持ちする菓子折り、お花や線香などが定番。故人の好物をお供えし「お空の上で食べているかな」などとご家族で話し合うのも、お彼岸らしいですね。
基本は、仏教の教えに基づく五供とよばれる以下のお供えものを意識しましょう。
- 花
- 線香
- ろうそく
- お茶
- 食べ物
お彼岸にやってはいけないこと
では、お彼岸にやってはいけないことはあるのでしょうか。お彼岸は仏教的な意味合いが強く、日本独自の文化であるお彼岸は飛鳥時代から始まったとされています。その後、平安時代には朝廷の年中行事となり、源氏物語にも描かれているそうです。そんな古くからの習わしであるお彼岸ですが、厳密にいうと「やってはいけないこと」は存在しません。しかし、古くからの迷信や常識により、避けられる行事や行動があります。
お宮参り
お彼岸にやってはいけないことの1つは、お宮参りです。お宮参りは、赤ちゃんが産まれた際に神社にお参りし、神様に赤ちゃんの誕生を報告する儀式。主に生後1ヶ月を目安にお宮参りをしますが、もしお彼岸が重なるようなら、時期をずらすのも良いでしょう。お宮参りをお彼岸にやってはいけないとされているのは、ご先祖さまを供養する期間に新たな命の成長を願うことが「不謹慎である」といわれているからです。
建前
建前は、お彼岸にやってはいけないことといわれています。建前とは、建造物の骨組みができたあとに新築の家に災難がないように神に祈念したり、祝宴を行うこともあるそうです。建前もまた、お宮参りと同様に神主が関与する儀式のため、お彼岸とは対照的な意味を持ち、昔から避けられてきたそうです。同じ意味で「引っ越し」や「新築祝い」も、新生活スタートの行事であるため、お彼岸に行うのは不向きだと言われてきました。
結婚式や披露宴
結婚式や披露宴などの「お祝いごと」は、お彼岸に行うべきではないといわれています。また、結婚式や披露宴は招待を受け参列・参加するものであり、多くの人のスケジュールを押さえ来ていただくものになります。そのため、お彼岸に招待をするとお彼岸の行事ができなくなり、ご先祖さまをおざなりにしていると考える人もいるそうです。
お見舞い
お彼岸にお見舞いをすることは、相手(病気やけがをしている人)に対し失礼な行為になってしまうおそれがあります。お彼岸はお墓参りをするのが通例であり、お見舞いをすることで不吉なイメージを与えてしまう可能性があります。相手に縁起の悪さを連想させ気分を害してしまわないよう、お見舞いは避けたほうが無難かもしれませんね。
納車
お彼岸に納車をすること自体はタブーではありませんが、納車をする際は縁起の良い日を選ぶ人が多いため、お彼岸は避けられているようです。お彼岸は「喪に服す」期間ではないため、考慮する人としない人がいます。しかし、やはりご先祖さまを供養したり感謝を伝えたりする期間中ということで、新しいことを始めるという意味合いを持つ納車も、避けられる傾向があるのですね。
水辺で遊ぶこと
お彼岸には、水辺に霊が集まるとされています。供養されなかった霊が水辺におり、水の中に生きた人間を引きずり込むという迷信があるのです。もちろん迷信であり、信じるか信じないかはその人次第ではありますが、不吉なためお彼岸には水辺遊びを避けるケースがみられます。なお、科学的根拠のある理由としては、お彼岸の時期は台風が多くなるため、水辺の事故を避けるために近づかないようにするというものもありますよ。
参考:石乃家
土いじり
お彼岸にやってはいけないこととして、土いじりがあります。しかし厳密にいうと、土いじりを避けるべきとされているのはお彼岸ではなく「土用の期間」(立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間)です。土用の期間は”土を司る神様が支配する”ため、土をいじることがタブーと考えられてきました。しかし、お彼岸に神事を避けるという常識から、土の神様にまつわる行動も避けるべきだと考える人がいるようです。
参考:お仏壇のはせがわ
まとめ
お彼岸にやってはいけないことや、基礎知識についてまとめました。お彼岸は年2回あり、それぞれでお墓参りやお供えなど、各ご家庭のご先祖さまを供養するための行事が行われます。お彼岸はご先祖さまのことを思い感謝するための期間なので、お祝いごとや新しいスタートを意味する行事が避けられてきました。しかし、喪に服すわけではないので、気にされなければ現実的な予定と調整すると良いでしょう。