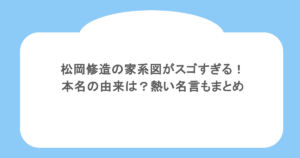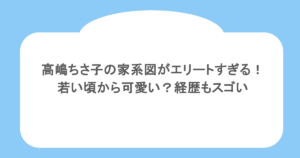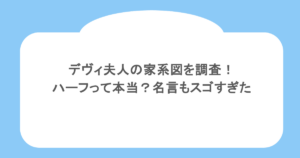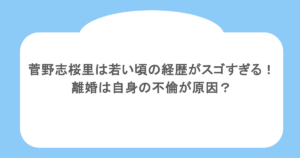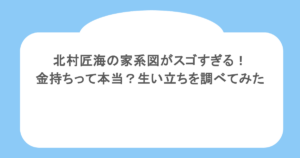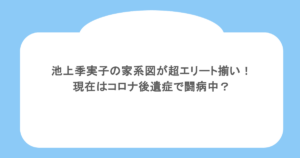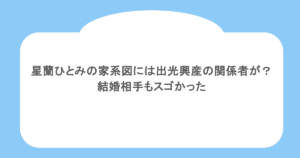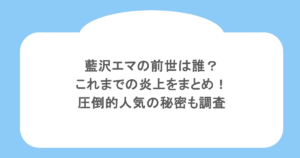金継ぎとは、欠けたり割れたりした器を漆で修復する伝統的な技法です。漆は天然素材で耐久性が高いので、食べ物を入れる器にも使える方法なんですよ。漆を使う金継ぎは「本金継ぎ」と呼ばれ、プロに依頼すると対応してもらえます。しかし、昨今では漆を使わずに自分で金継ぎをするキットが販売されており、より金継ぎが身近なものになってきました。そこでこの記事では、金継ぎの基本的な情報ややり方、またできない素材について解説したいと思います。
金継ぎとは?
金継ぎは、漆を使って器を修復する方法です。「金」という言葉が使われていますが、実はほとんどが漆で修復されており、金は最後の仕上げのときに使うのだそうです。代々使われてきた器を直して長く使いたい人や、思い入れのある食器を捨てたくない人が、金継ぎをプロに依頼することが多いようです。
【参考サイト:日本金継ぎ協会】
金継ぎで使われる漆は、漆の木やブラックツリーから採れる成分です。金継ぎで使うには、その漆を乾燥させ強力な硬化作用も持たせた状態にします。人体に無害な協力接着剤の役割を果たしてくれるのですね。
金継ぎの基本のやり方
金継ぎの基本のやり方を、プロの方法と自分で行う方法に分けて見てみましょう。代々大切に使われてきた食器などは、プロに依頼するのがもっとも安全な方法ですが、最近では自分で金継ぎができる方法もあります。より手軽でコストをかけずに食器を直したい人は、金継ぎキットを購入してみると良いでしょう。プロの方法と自分で行う方法を比較しながら、ご自身に合う方を選んでみてください。
プロが行う金継ぎとは
プロが行う金継ぎは、漆を使った「本金継ぎ」です。使うものは、漆と小麦粉。2つを練り合わせ接着剤にします。欠けた部分を接着したら、隙間が空いている部分に木の粉と漆を練り合わせたものをパテのようにして塗り、均します。接着作業が終わると「室(むろ)」という温湿度が管理された部屋で器を保管し、乾燥させます。器が完全に乾いてからさらに数週間後、仕上げ作業として漆の上から金粉をふって、完成です。
自分で行う金継ぎとは
自分で行う金継ぎは、手軽にできるキットを用いるものです。今回は、ハンズで販売されているキットをご紹介します。この「金継ぎ初心者セット」を使うと、手順は以下のようになります。
| 1 | 欠けている部分に透漆を塗る(はみ出た部分はふき取る) |
| 2 | 箱の中で一晩乾燥させる |
| 3 | 乾ききったら取り出す |
| 4 | 部分修復用の「刻苧漆」を作り、穴の開いた部分を埋める |
| 5 | さらに1~2週間ほど乾燥させる |
| 6 | 乾ききったら取り出す |
| 7 | 「錆漆」で細かい穴や小さい段差を埋める |
| 8 | さらに4~5日ほど乾燥させる |
| 9 | 弁柄漆を塗ってコーティングする |
| 10 | 金粉を蒔いて完成 |
自分で金継ぎを行う際には、接着剤となる成分を練り合わせて作る工程が多いので、時間や場所を確保するようにしましょう。
金継ぎでできないものは?
金継ぎでできないものは、以下の素材です。
| 金継ぎでできないもの | 理由 | 対処法 |
| 土鍋 | 漆で修復した部分を火にかけられないため | 火にかけない土鍋の使い方をする(食器や小物入れなど) |
| ガラス | 漆との相性が悪く強度が弱くなるため | ガラス用の漆を用いる ガラスの金継ぎに対応している業者に相談する |
| 花瓶 | 漆で修復した部分は長時間水に浸けておくことができないため | ドライフラワー用の花瓶にする 水が浸からない部分(花瓶の上の方など)のみ修復する |
陶器は金継ぎで修復することができますが、土鍋のように直火で使用したり、長時間(1時間ほど)水に浸ける使い方をしたりする場合には、金継ぎは推奨されないそうです。
まとめ
金継ぎとは何か、基本のやり方やできない素材について解説しました。金継ぎは業者に依頼するのが一般的でしたが、最近では自分で修復する道具が販売されています。より手軽でコスパ良く器の修復ができる方法ですので、ぜひ検討してみてください。大切な器を、漆で修復しながら長く使うことは、サスティナブルで素敵なことですよね。金継ぎを活用して、思い入れのある器と一緒に、末永く食事ができると良いですね。